今回は日々の支援現場での「問い」に目を向けてみたいと思います。利用者さんとの会話や、スタッフ同士のやりとりで飛び交う質問の数々…。質問をすること自体は大切ですが、その「問いの質」について考えたことはありますか?
例えば、利用者さんの作業がひと段落しそうな場面で、隣の同僚に「次はこの方に何をしてもらえばいいですか?」と聞いてしまった経験はないでしょうか。状況を一緒に見ていたはずなのに、つい相手に答えを委ねてしまう
こんな「もったいない質問」を、私自身もつい口にしてしまいそう、口にしていることがあります。
本記事では、スタッフが利用者さんやお互いに投げかける質問の質を高めることの重要性について、実例や日々の気づきを交えながら考えてみます。問いの質を見直すことで生まれる相互理解や成長、そしてそのためのヒントを一緒に探っていきましょう。
Contents
なぜ問いの質が重要なのか

支援の現場ではコミュニケーションが命です。利用者さんの状況を把握し、適切なサポートを提供するために、私たちは日々たくさんの質問を投げかけます。実際、福祉や医療の現場では「相手が何を考えているか、何を不安に思いどうしたいのかを知るためには、質問するしかない」ため、「よい質問をすることがなにより大切」です。適切な質問によって相手の本音を引き出し、理解を深めることができるからです。
質問の力は利用者さんとの関係だけでなく、スタッフ同士の連携にも大きく影響します。自己啓発作家アンソニー・ロビンズも「質の高い質問が、質の高い人生を作る」と述べています。そして職場においても、質の高い問いかけは相手との意思疎通を円滑にし、新たな気づきや解決策を生む原動力になります。
一方で、何気なく発した質問が相手にプレッシャーを与えたり、誤解を招いてしまうこともあります。だからこそ、日頃から「問いの質」を意識することが大切なのです。
支援現場で見かける「もったいない質問」

それでは、具体的に「問いの質」が低いケースとはどんなものでしょうか。私たちの支援現場でも時々見かけるのが、自分で考えれば答えが出そうなことを他人に丸投げしてしまう質問です。
冒頭で触れた「次はこの方に何をしてもらえばいいですか?」という問いかけは、その典型でしょう。利用者さんの様子を見ていたスタッフなら、次に何をするべきかある程度見当がつくはずです。しかし、咄嗟に同僚に尋ねてしまうのは、自信のなさや判断ミスへの不安、あるいは単に考える手間を省きたい気持ちの表れかもしれません。
こうした質問は一見丁寧に指示を仰いでいるようにも見えますが、実は「もったいない」の一言に尽きます。まず、質問された側(同僚や上司)は「自分で考えればわかるのでは?」と感じるかもしれません。忙しいときにこのような質問を受けると、内心ストレスを感じることもあるでしょう。また、利用者さん本人にとっても、目の前でスタッフ同士が「次は何をさせる?」と相談しているのを聞くと、「自分は何をやらされるんだろう」と不安になったり、主体性が損なわれたりする可能性があります。
さらに言えば、その質問をしたスタッフ自身にとって大きな損失です。本来なら自身で判断して行動し、経験値を積むチャンスだったかもしれないのに、それを逃してしまうからです。「何をすればいいですか?」とすぐ聞く癖がついてしまうと、いつまで経っても現場の勘や判断力が養われません。
もちろん、わからないことを素直に聞くこと自体は悪いことではありません。しかし、自分の中で何も考えずに質問してしまうと、それは単なる「丸投げ」になってしまいます。現場では「質問はどんどんしてね」と教育されることも多いですが、何でもかんでも聞けばいいわけではないのです。
聞くときも自らが見た感覚やそこから生まれた考えを相手に伝えたうえで意見を仰いだりすると良いでしょう。
質の高い質問が生む相互理解と成長

では、反対に「質の高い問い」とはどんなものでしょうか。一言で言えば、相手への思いや自分なりの考えが込められた問いかけです。質の高い質問は、受け手に「真剣に向き合ってくれている」と感じさせ、建設的な対話を生み出します。
例えば先ほどの場面でも、「次は何をすればいいですか?」ではなく「〇〇さん(利用者)今日は作業が早く進んでいます。このあと少し休憩を挟んだ方が良いでしょうか? それとも集中できているようなら、もうひとつ別の作業をお願いしても大丈夫そうでしょうか?」と尋ねてみるのはどうでしょう。こうすれば、一緒に状況を見ている同僚にも、自分なりに利用者さんの様子を観察して考えていることが伝わります。質問を受けた側も「じゃあ一度本人に意向を聞いてみようか」など、具体的に検討しやすくなるでしょう。
このように背景や意図が伝わる質問は、職員同士の相互理解を深めます。同僚に対して自分の視点や悩みを共有することで、お互いに納得感を持って次の対応を決めることができます。また、自分が考えた上で問いかけることで、相手からの信頼も生まれます。単なる丸投げではなく「一緒に考えてほしい」というスタンスが伝われば、受け手も真摯に答えようという気持ちになるものです。
利用者さんに対する質問の質も同様に大切です。例えば作業中に利用者さんの手が止まったら、「どうしましたか?」と尋ねるだけでなく、表情や様子から「少し疲れましたか?休憩しましょうか?」と問いかけてみましょう。そうすることで相手も答えやすくなり、本当の気持ちを打ち明けてくれるかもしれません。
選択肢を与える質問も有効です。例えば「次にA作業とB作業、どちらからやりますか?」と尋ねれば、ご本人の意思を尊重しつつ主体性を促せます。常にこちらから指示するのではなく、質問によって相手の考えを尊重する姿勢が信頼関係につながります。
質の高い問いがもたらすものは、何も相手への理解だけではありません。実は質問する側である私たち自身の成長にも大きく関わっています。よく「教える側が一番学べる」と言いますが、「質問する側こそ一番考える」のだと思います。相手に問いを投げるとき、自分の中で状況を整理し、ベストな聞き方を工夫します。そのプロセス自体が、支援員としての洞察力やコミュニケーション力を磨くトレーニングになっているのです。
質問の質を高めるためのヒント
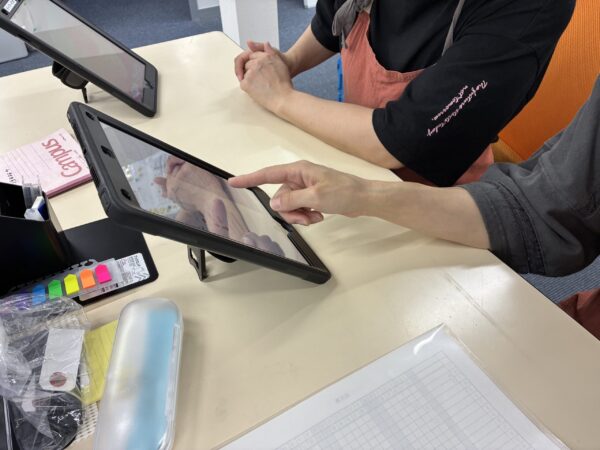
では、具体的に日々の現場でどうすれば問いの質を高められるでしょうか。いくつかヒントを挙げてみます。
1. 質問する前に「少しだけ考える」
何か疑問が浮かんだとき、すぐ口に出す前にほんの数秒立ち止まってみましょう。その場で自分なりの考えや判断を巡らせてみるのです。「自分は今、何が分かっていて、何が分からないのか」「自分なりに答えを出すとしたらどうするか」――このように頭の中で整理してみるだけで、質問の内容はぐっと洗練されます。先ほどのCRECIOS社の記事でも、「質問の精度を高めるには特別なスキルは要らない。ただ質問する前に少しだけ考えることが大切だ」と指摘されていました。
例えば「この利用者さん、今日は落ち着かない様子だけどどうしたらいいだろう?」とすぐ他人に聞くのではなく、まず自分の目で観察し「〇〇さんはいつもより手元が震えているな。体調が悪いのかも?」と仮説を立ててみます。その上で「△△さん(同僚)、〇〇さん少し体調が優れないかもしれません。休憩を提案した方がいいでしょうか?」と聞けば、相手も状況を把握しやすく、建設的に答えやすくなるでしょう。
2. 背景と意図を添えて質問する
自分の質問の意図や、それまでに考えたことを相手に伝える癖をつけましょう。いきなり「どうしたらいいですか?」ではなく、「○○という状況なので△△かと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?」という風に、背景と自分の考えを添えるのです。これは職員同士の会話だけでなく、上司への相談や他機関への問い合わせでも有効です。前提を共有してから質問することで、相手も答えやすくなり、お互い時間の節約にもなります。
例えば、利用者のAさんが作業中に居眠りしてしまう場合でも、「Aさんは朝早くから家の手伝いをしていて午後には眠くなるようです。この場合、無理に起こすより一度休憩を促した方が良いでしょうか?」と背景を添えて質問するだけで、相手は状況を把握しやすくなり、より的確なアドバイスが返ってくるでしょう。
3. 同僚や後輩の質問には考える機会を与える
自分が質問する場面だけでなく、同僚や後輩から質問を受けたときの対応も工夫できます。もし相手の質問が明らかに「少し考えれば分かりそう」な内容であれば、すぐに答えを教えるのではなく一緒に考える方向に促してみましょう。
例えば後輩から「この利用者さん、どう対応したらいいですか?」と漠然とした質問を受けたら、「そうだね、今何か自分で試してみた?」と優しく聞き返してみるのも一つの方法です。何も試していない場合、本人も「まずやってみなくちゃ」と気づくきっかけになるかもしれません。また、質問の内容によっては「君はどう思う?」「今の状況を教えてくれる?」と問い返すことで、相手に考えを言語化してもらうのも有効です。頭ごなしに「自分で考えて」と突き放す必要はありませんが、考えるヒントを与える対応を心がけると、互いに成長できるやりとりになります。
ある先輩社員は「努力のない質問には即答せずにいると、そのうち『自己解決しました』と報告が来るようになり、質問の質も向上した」と語っています。すぐに答えを与えないことで、質問者自身に考える余白が生まれ、その分だけ成長の機会になるというわけです。私たちも日常の中で、「すぐ答えを教えない勇気」を持つことで、後輩や同僚の自主性を育みたいですね。
4. 利用者さんには傾聴とオープンクエスチョンを
利用者さんとの対話では、こちらから問いかけるだけでなくしっかり耳を傾けること(傾聴)も忘れずに。相手の返答を最後まで遮らずに聞くことで、新たな疑問や気づきも生まれます。そして質問の種類にも気を配りましょう。イエスかノーで答えられる質問ばかりだと会話が広がりません。オープンクエスチョン(自由に答えられる質問)を織り交ぜてみてください。「楽しいですか?」ではなく「作業をしてみてどんな気持ちですか?」、「大丈夫?」ではなく「どこかしんどいところはないですか?」という具合に聞くと、利用者さんも自分の言葉で気持ちや考えを表現しやすくなります。
おわりに:問い直す習慣をLumoで
就労継続支援B型事業所Lumoで働く私たちスタッフは、日々さまざまな形で利用者さんをサポートしています。その中で「質問」は、相手を知り共に成長していくための大切なツールです。だからこそ、一度立ち止まって自分の問いかけを見直してみませんか。
支援の現場では、つい慣習や先入観で行動しがちです。「分からなければすぐ聞く」「利用者さんにはこちらから指示すべき」――そんな思い込みをあえて問い直してみる価値があります。例えば「今、本当に聞く必要があるのか?」「自分ならどう判断するか?」と自問してみるのです。その積み重ねが、支援の質をワンランク上げる原動力になるはずです。
質の高い質問は、互いの理解を深め、責任感と信頼感に満ちたチームワークを育みます。スタッフ同士がお互いに考えを伝え合い、利用者さんとも丁寧に対話を重ねていくことで、Lumoという職場全体がより温かく前向きな空気に包まれるでしょう。
最後に、少しだけ自分自身にも問いかけてみてください。「明日の自分は、どんな良い質問ができるだろうか?」――その答えを探すプロセスこそが、私たち自身の成長にほかならないのではないでしょうか。明日からの支援現場で、ぜひ皆さん一人ひとりの「質問力」を発揮してみてください。
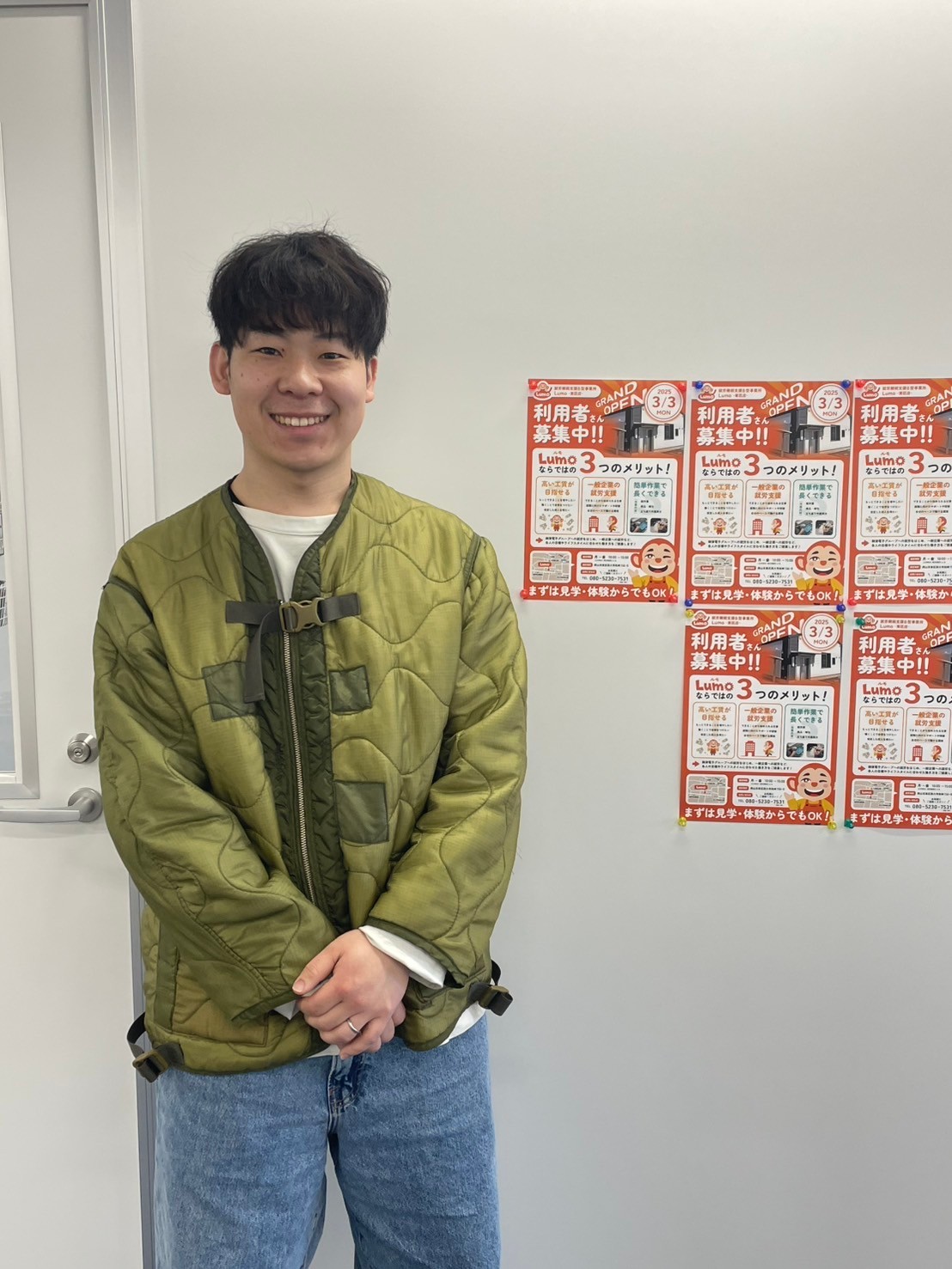
はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です
Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。
――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。
定員20名なのに見学待ちの行列。
毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。
どうして行列ができるの?
- “支え合う”という文化
ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。
だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。
▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)
- 仕事を“楽しく”設計
ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。
「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長
初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。
成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。
これからブログで発信すること
- 利用者さんの成長ストーリー:
小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:
就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:
見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。
最後に
「みんな違って、みんながいい」――
そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。
これは私の原動力であり、Lumoの未来です。
ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!
