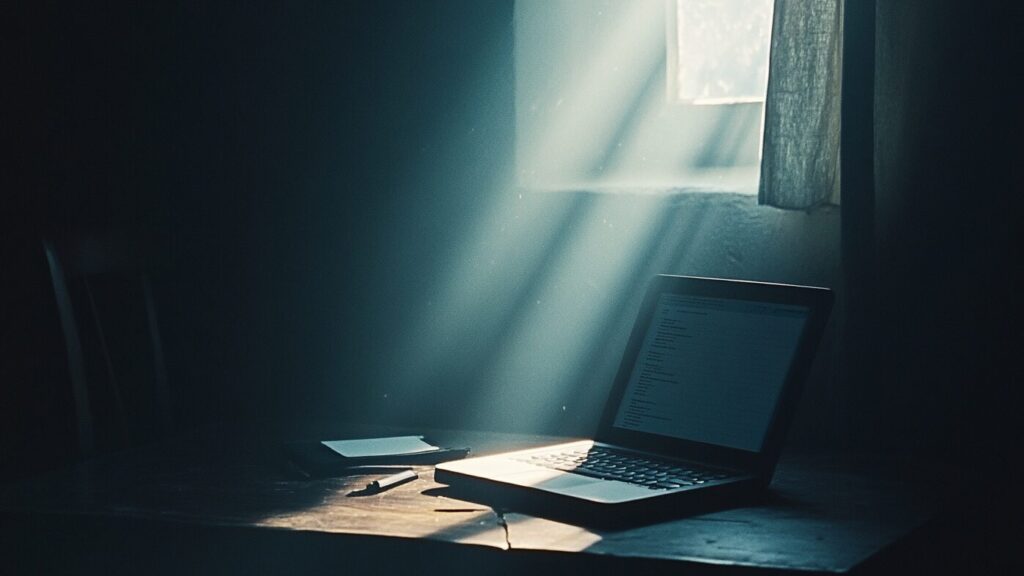2025年5月、岡山市の就労継続支援A型事業所を運営する特定非営利活動法人と理事が、利用者5人に対する4カ月分の賃金を支払っていなかったとして書類送検されました。
これは、就労支援の現場に関わる私たちにとって、決して他人事ではない重大な問題です。
就労支援事業所は本来、一般就労が困難な方や一般就労を目指す方に「働く場」を提供するとともに、障がい者が社会とつながるための大切な拠点であるはずです。
それにも関わらず、このような不誠実な対応があったことは、利用者やそのご家族、そして障がい者支援制度そのものの信頼を損なうもので、非常に残念でなりません。
本記事では、このような事件がなぜ起こってしまったのかを考察するとともに、私たちLumoが就労支援において果たすべきミッションについて再確認していきます。
Contents
なぜ未払いが起きたのか
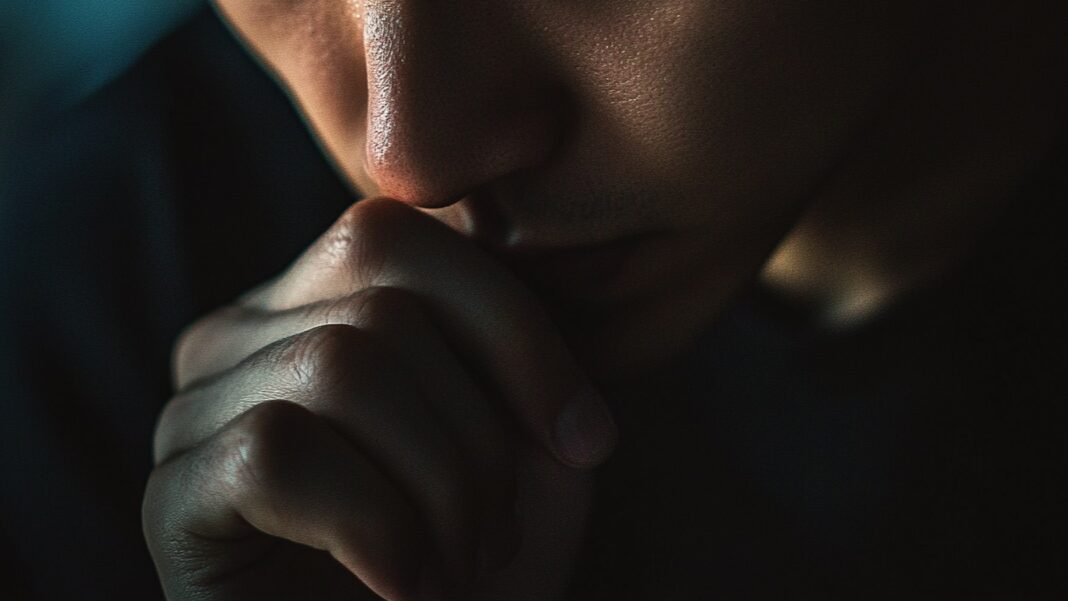
このような利用者からの信頼を損なってしまう事が起きてしまったのか。
考えられる要因は2つあります。
資金繰りの悪化
就労支援事業所の経営が苦しい状況にあることも事実です。
特に、A型事業所は雇用契約を結ぶため最低賃金の支払い義務があります。
しかし、近年の最低賃金の上昇、物価高騰、人手不足といった要因が重なり、事業所の経営はますます厳しくなっています。
帝国データバンクによると、2023年度には障がい者支援事業者の倒産や休廃業・解散が71件に上り、過去最多を更新しました。
また、2022年度では約4割の事業所が赤字経営に陥っているという調査結果もあります。
資金繰りが厳しい中で、賃金の支払いが後回しにされ、結果として法令違反に至った可能性は否定できません。
事業所の本来の存在意義が形骸化
まず「働く」という言葉の意味は、単に労働力を提供するだけでなく、「社会に貢献し、自己成長や生活の維持などを目的とし、職業として時間や体力を費やし、その対価として収入を得ること」です。
就労支援事業は、障がい者に働く場や機会を提供する事業ですが、そういった本来の存在意義を果たせていなかった可能性があります。
実際、国からの給付金や補助金を得ること自体が目的化してしまい、利用者を形式的に雇用しているだけの事業所も存在することは以前から指摘されており、
過去には、利用者や職員数の水増しが発覚して破綻に追い込まれたケースもあります。
↓詳しくはこちら↓
また、A型事業所は雇用契約を結ぶため、賃金未払いは労働基準法違反となります。
就労支援事業所としての本来の役割は何なのか、利用者が安心して働ける環境とは。
しっかりと理解した上で事業所の運営基準を強化することが求められます。
今回の事件の原因が必ずしも上記2点に当てはまるとは限りませんが、このような事業所が存在するのこともまた事実です。
就労継続支援事業所が果たすべき役割

今回の事件を受けて、私たちが果たすべき役割を改めて見つめ直しました。
顧客を見つけ、仕事をつくる
この問題の本質は「障がい者の賃金を支払う原資をどう確保するか」にあります。
補助金に依存するだけではなく、障がい者が行える仕事を事業所側がしっかりと開拓し、社会的価値を生む仕事として成立させていくことが、運営の基盤となります。
地域企業や団体と連携し、障がい者の特性に合った仕事を設計・受託し、仕事の対価として適正な賃金を支払う。
このサイクルを確立させることこそ、就労支援事業所に求められる「責任ある経営」です。
透明性のある運営を行う
運営方針、基本的な法令、利用者の状態やなど様々な情報をスタッフ全員が共有・理解した状態につくることが重要です。
例えば、スタッフに対して労働基準法や障害者総合支援法など、基本的な法令に関する定期研修を行うことで、事業所全体の法令尊守への意識づけになります。
また、給付金を得るためにむやみに利用者を増やすのではなく、利用者にとって実のある訓練や業務、質の高いサポートを提供することが求められます。
そして、勤務実績や支援内容、業務成果などの記録を、電子的かつ正確に管理・保存する体制を整える。
これらの取り組みは、透明性と信頼性のある運営を実現するために欠かせません。
利用者の声を反映し、支援の質を高める
何度も言いますが、就労支援事業の役割とは、一般就労を目指す方や一般就労が難しい方が安心して働ける場を提供することです。
物の置き場や席の配置、困っていることや悩んでいることなど、利用者が小さなことでも意見を述べられる環境を作りましょう。
Lumoでは、月1回の個別面談を行ったり「なんでも聞いてくださいね」といった声掛けを毎日するようにしたりなど、利用者との距離感を大切にしており、
利用者から寄せられた声は、スタッフ全体で共有し、可能な限り環境改善に反映させています。
まとめ

今回は、A型事業所による賃金未払い事件がなぜ起こってしまったのかを考察するとともに、私たちLumoが就労支援において果たすべきミッションについて再確認していきました。
| 〇なぜ未払いが起きたのか
・最低賃金の上昇、物価高騰、人手不足といった要因で資金繰りが悪化 ・国からの給付金や補助金を得ること自体が目的化してしまい、事業所本来の存在意義が形骸化 〇就労継続支援事業所がやるべきこと ・顧客を見つけ仕事をつくり、障がい者の賃金を支払う原資を確保する ・透明性のある運営を行う ・利用者の声を反映し、支援の質を高める |
LUMOは、「社会と障がい者をつなぐ」ことをミッションとし、B型事業所を運営しています。
定員がまもなく満員となる中で、すでに社会に貢献できる人材を輩出し始めており、次のステップとしてA型事業所の設立を本気で検討しています。
就労支援事業は、「支援する側・される側」という一方向的な関係ではなく、共に社会の一員として暮らしていく「共生」の関係であるべきです。
安心して働き、賃金を得て、生きがいを感じられる社会をつくるには、私たち事業者が経営と支援の両面から課題に取り組む必要があります。
LUMOは、これからも社会課題に正面から向き合い、現場の声に耳を傾け、責任ある経営と支援を両立させながら、真の意味で「つながる福祉」の実現を目指してまいります。