Contents
常識とは何か、疑うことの意味
「常識」と聞いて何を思い浮かべますか?多くの人が当たり前だと思っているルールや考え方のことかもしれません。常識とは、言い換えれば「誰もが知っていて当然とされること」です。しかし、その「当然」は時代や文化が変われば驚くほどあっさりと変わってしまうものでもあります。
例えば昔は常識だったことが、今では非常識だと言われるようになった例も少なくありません。逆に、今当たり前とされていることも、未来の社会では通用しなくなっているかもしれません。こう考えると、私たちが「常識だ」と信じていることも、実は絶対の正解ではなく、単なる一つの考え方に過ぎないのかもしれません。だからこそ、一度立ち止まって常識を疑ってみることには大きな意味があるのです。
常識を疑うと聞くと、何でもかんでも逆らうような印象を持つかもしれません。しかしそうではなく、好奇心を持って「本当にそうなのか?」と考えてみるということです。考えた先で良いことはもっと良くしていく、改善が必要な事なら協力し合って良い方向に繋ぐことができる。私たちが普段当たり前だと思っていることに疑問を投げかけてみれば、新しい発見やより良いアイデアに出会えるかもしれません。常識を疑うことで私たちの日常や価値観はどのように変わるのでしょうか。ここから一緒に考えていきましょう。
違うと思っても否定せず、受け止めてプラスアルファを考える
日常生活や仕事の中で、自分の考えとは違う意見や方法に出会うことがあります。そんなとき、つい「それは違うんじゃない?」と否定したくなるかもしれません。確かに、自分の中の常識から外れる提案を聞くと、不安になったり抵抗を感じたりするものです。
しかし、相手の考えが自分と違うからといって、すぐ否定してしまってはお互いの成長の機会を逃してしまいます。そこで大切なのが、一度「そういう考え方もあるんだ」と受け止めてみることです。(僕はこの考えが出来ず、数えきれないほど上司に歯向かってしまった経験あり)受け止めるとは、相手の意見に必ずしも全面的に賛成するという意味ではありません。そうではなく、違う考え方も尊重して認めてみるという姿勢です。
例えば、職場で後輩が自分とは異なるやり方を提案したとしましょう。そのときに「それはダメだ」と切り捨てる代わりに、まずは最後まで話を聞いてみます。そして、「なるほど、そういう手もあるのか」と一度受け入れて考えてみるのです。
その上で、自分の経験や知識をプラスアルファとして付け加えて、新しいアイデアを一緒に考えてみます。このようにすれば、ただ対立するのではなく、お互いの長所を生かした解決策が見つかるかもしれません。
実際にこの姿勢を試すために、次のステップを心がけてみてください。
- 最後まで話を聞く: 違う意見に出会ったら、まず相手の話を途中で遮らず最後まで聞きましょう。相手が何を考え、なぜそう考えるのかを理解する姿勢が大切です。
- 一度受け入れてみる: 自分と異なる考えに触れたら、「そういう考え方もあるのだな」と一度受け入れてみます。すぐに否定するのではなく、まずは相手の視点を認めることで、新たな気づきが得られることがあります。
- プラスアルファを考える: その上で、自分の考えや知識も踏まえて、「ではこうしてみたらどうだろう?」とプラスアルファのアイデアを提案してみましょう。互いの意見を組み合わせることで、より良い解決策が生まれるかもしれません。
このように、違う意見に対して否定から入らず一度受け止めてみるだけで、議論は前向きになり、新しい発想が生まれやすくなります。自分一人では思いつかなかったプラスアルファが見つかることもあるでしょう。この小さな心がけが、お互いの理解を深め、より良い関係や成果につながるのです。
ここで大切なのは上記に記した考え方を自分も相手も持っておくことであり、これは相手に求めずとも自分自身が考え方を変えようとお互いが思っていれば成り立ちます。
世代を越えた交流がもたらす価値観の変化と多様性の広がり
私たちが「常識」だと思っていることは、実は世代によっても大きく異なります。親世代・祖父母世代の常識と、今の若い世代の常識が噛み合わず、お互いに驚くこともあるでしょう。例えば、今の若者にとって当たり前のテクノロジーや価値観が、上の世代には理解しがたいことがあります。逆に、昔は当たり前だった習慣が、現代の若者には新鮮に映ることもあります。子供の育て方なども同じことが言えるでしょう。
このように世代間ギャップを感じるとき、単に「最近の若者は…」「昔の人は頭が固い」と批判し合うのは簡単です。ですが、そこで立ち止まってお互いの話を聞いてみると、価値観の背景にはその世代ならではの経験や社会環境があることがわかります。
世代を越えて交流することで、自分の常識が絶対ではないことに気づかされます。若い世代は年長者から昔ながらの知恵や忍耐強さを学び、年長者は若い世代から新しい発想や柔軟性を学ぶかもしれません。お互いの常識がぶつかるのではなく、交わることで、多様な価値観が生まれ、広がっていくのです。
世代を超えた交流は、まさに多様性(ダイバーシティ)を体感する機会でもあります。(ダイバーシティについてもまたブログを書きます)自分とは異なる時代背景を持つ人と話すことで、「当たり前」が人それぞれ違うことに気づきます。この気づきは、日常のささいなことから社会全体の問題まで、物事を様々な角度から考える力を養ってくれます。
Lumoが大切にしている「知識より目の前の“あなた”を大切にする姿勢」
Lumoでは、「障がい、福祉の知識よりも目の前の“あなた”を大切にする」という姿勢を大事にしています。これは、たとえ豊富な知識や常識があったとしても、それにとらわれて相手を見失ってはいけない、という考え方です。
人と向き合うとき、頭の中にある教科書通りの解決策や固定観念だけで判断するのではなく、目の前の相手の声に耳を傾け、その人を理解することを優先します。知識は便利なツールではありますが、それだけに頼っていては本当の意味で相手と心を通わせることはできません。
たとえば、マニュアルや理論では「正しい」対応策があったとしても、相手の状況や気持ちによっては当てはまらないこともあります。そんなときは、持っている知識を一度横に置いて、目の前のあなた(相手)が何を求めているのかに心を配ります。
このように「知識より目の前のあなたを大切にする」姿勢を心がけることで、相手に本当に寄り添った対応や、新しい解決策を見つけることができます。常識や知識に囚われずに人と接することで、その場その場に合った柔軟な発想も生まれてくるでしょう。Lumoが大切にするこの姿勢は、常識にとらわれず「今、ここ」にいる相手を大事にする生き方とも言えます。
まとめと読者への問いかけ
ここまで、常識を疑うことの大切さについて様々な角度から見てきました。常識は社会で生きる上で大事な指針ではありますが、それに固執しすぎると新しい発見や成長のチャンスを逃してしまいます。自分と違う意見を否定せずに受け止めてプラスアルファを考えてみることで、新たな発想が生まれることもあります。また、世代を越えた交流から得られる多様な視点は、私たちの価値観を大きく広げてくれました。Lumoが大切にする「知識より目の前のあなたを大切にする姿勢」も、相手を理解し共感するためには常識にとらわれない柔軟な心が必要だということを教えてくれます。
皆さんにとって「当たり前」になっていることの中に、もし一つだけ疑ってみるとしたら何がありますか?毎日の習慣や信じて疑わないルールを、ほんの少し違う角度から眺めてみると、新たな発見や変化が生まれるかもしれません。今日からぜひ、身の回りの「常識」を一つ選んで、疑ってみる一歩を踏み出してみませんか?その小さな一歩が、あなた自身の世界を広げる大きなきっかけになるかもしれません。
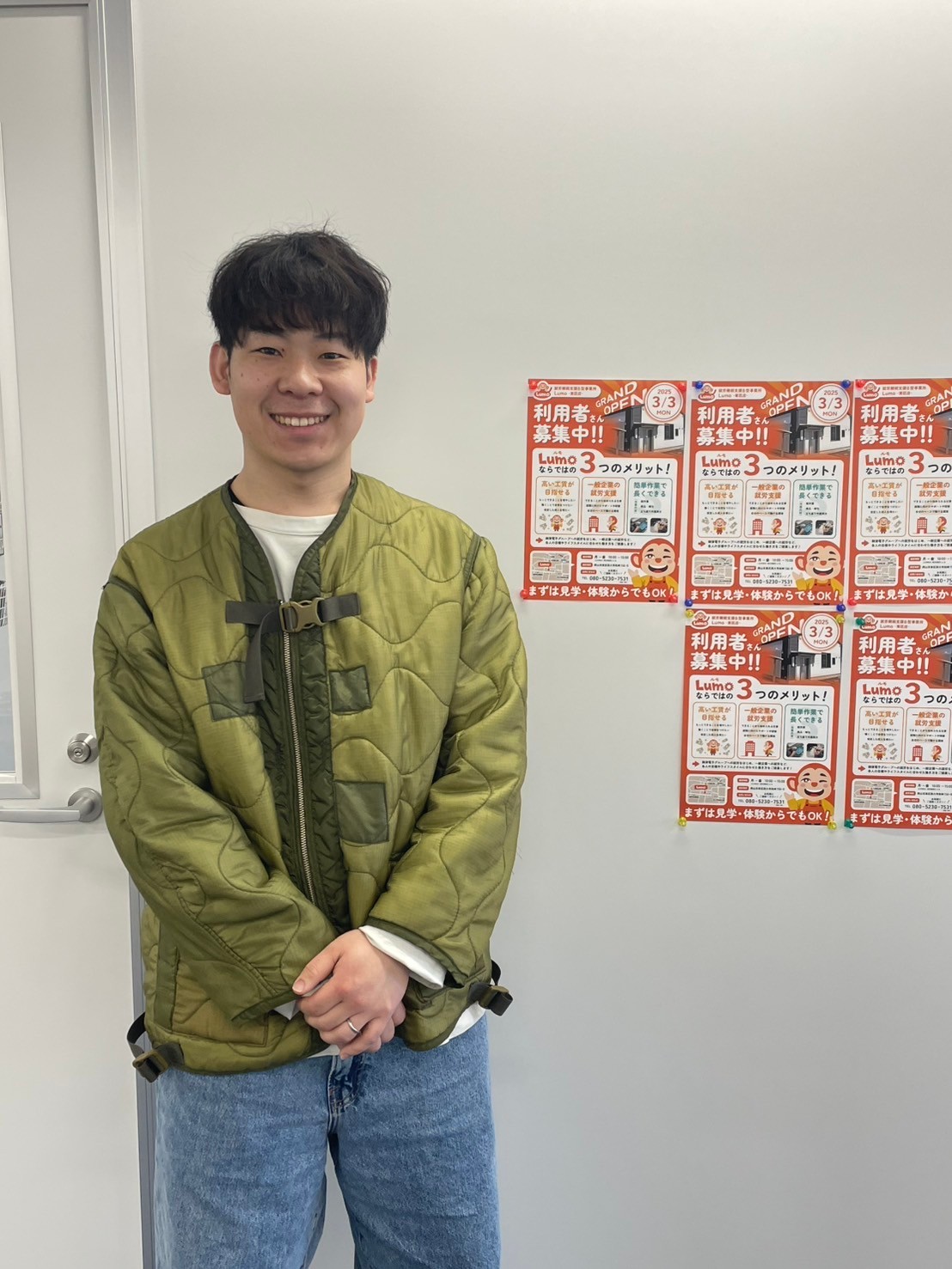
はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です
Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。
――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。
定員20名なのに見学待ちの行列。
毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。
どうして行列ができるの?
- “支え合う”という文化
ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。
だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。
▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)
- 仕事を“楽しく”設計
ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。
「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長
初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。
成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。
これからブログで発信すること
- 利用者さんの成長ストーリー:
小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:
就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:
見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。
最後に
「みんな違って、みんながいい」――
そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。
これは私の原動力であり、Lumoの未来です。
ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!
