「努力」は全員ができる平等の機会ではない
「努力は裏切らない」──よく聞く言葉です。でも、努力そのものを“出せる状態”まで整えることは、誰にとっても同じ難易度ではありません。
岡山市東区の就労継続支援B型Lumoでは、日々の支援の中でその事実に何度も出会います。この記事では、努力の前にある“土台”を見直すことで、利用者さんもスタッフも無理なく力を発揮できる現場づくりを提案します。
Contents
1|努力は土台しだい──3つのレイヤー
同じ「頑張る」でも、人によって必要なエネルギー量が違う。その差を生むのが、以下の3つのレイヤーです。
- 環境レイヤー:交通・天候・住環境・経済状況・家族関係など。朝からの通所が難しい日は、努力が足りないのではなく移動コストが高すぎるだけかもしれません。
- 身体・認知レイヤー:体調の波、感覚過敏、特性による疲労のたまり方。10分の集中が人によっては全力疾走に匹敵します。(ウルトラマンでさえも3分しか戦えません)
- 関係性レイヤー:叱責の記憶、失敗体験、安心できる人の有無。「大丈夫だよ」と言える相手が1人いるだけで、努力の出力は大きく変わります。
この土台を整えずに「もっと頑張ろう」は、足場板のない工事現場で急かすのと同じ。Lumoでは、努力を求める前に努力しやすい場をつくることを優先しています。
2|「不公平さ」を見て見ぬふりをしない
世の中には、努力を積み上げやすい人と、そうでない人がいます。それは意志の強さではなく、初期条件の差です。例えば、睡眠不足・痛み・金銭不安・孤立──これらは努力の燃料を奪います。だから現場では、公平(同じものを配る)ではなく、公正(必要に応じて支える)を目指します。
「あの人はサボっているのでは?」と感じたら、まず問いを反転させます。
「サボっている」のではなく、「エネルギーの漏れどころ」があるのかもしれない。
3|現場でできる再設計:Lumoの小さな実践
(1)時間の単位を“分解”する
「午前中ずっと集中」は難しくても、「15分×3セット」なら行ける。タイマーとチェック表を用意し、達成ごとに小さな完了感を積み上げます。(あくまでも案)(Lumoでも実践はできていない)
例:プラスチック検査なら、15分作業→5分休憩→15分作業のようにリズムを先に決める。(あくまでも当事者本人が最終決定)
(2)選べる導線を用意する
「A:座って検査」「B:立ってカット」など、同じゴールに向かう複数の入口を用意。日によって体調が違っても、努力の形を選べます。
(3)“見通し”を見える化する
「次は何をすれば?」という不安は、努力の燃費を悪くします。作業が終了しそうな時は次の作業の準備をする、作業の合間には自分のペースで休める等 自分で進めた気持ちを途切れさせない工夫をしています。
(4)ごはんと睡眠を、支援の一部に
空腹や眠気は、努力の残量を一気に削ります。
Lumoでは、昼食の持参・注文の選択肢や短時間の仮眠の許容(薬の副作用で寝てしまう人も)など、生活の土台に手を伸ばすことを“支援”と捉えています。
(5)フィードバックを“点”ではなく“線”に
「今日はOK」「今日はダメ」だけだと、努力はギャンブルになります。
月次のふり返りで、どこで調子が落ちたか/何が助けになったかを一緒に言語化。次の月に持ち越せる再現性を作ります。
Lumoではサービス管理責任者が月1でご利用者様と1対1で対話する時間を必ず作っています。
4|常識の裏側:「標準」は本当にみんなにやさしいのか?
「みんなが使っている=正しい」とは限りません。体格や感覚特性、経験の差によって、同じモノでも使いやすさは大きく変わります。(カップヌードルが一番売れているからといって満場一致で美味しい訳ではないですよね)
“人をモノに合わせる”のではなく、“モノと導線を人に合わせる”。これを前提に設計すると、努力の消耗は一気に減ります。
- 姿勢の選択肢:前傾/直立/足台の有無など、作業姿勢を複数用意。
- 感覚の負荷:照度・音・匂いを調整できるようにする(耳栓やライト、換気の工夫)。
- 道具のカスタム:グリップの太さ、置き位置、利き手導線の左右入れ替え。
“普通”を一度止めて問い直す。これも努力の土台づくりです。
5|スタッフとの関わり方:声かけより“余白設計”
支援は“声をかけること”だと思われがちですが、Lumoで大切にしているのは余白です。
「ちょっと待って」の一言が連鎖して混乱した日がありました。
そこで、“待ち”が発生しにくい配置に再設計しました。
- レイアウトの更新:作業動線を短くし、確認が必要な人の席をスタッフ動線の手前に。
- 合図の統一:ワンフロアで伝えづらいことや他者のスケジュールがわかるようにタブレットやパソコンで連絡共有ができるようにシステム導入。
- 質問の型:「AとBのどちらが良いですか?」「わかることでも再確認」と、自分の案を添えて聞く癖をチームで共有。
その結果、“待ち時間のイライラ”が減少。努力は増やしていないのに、手応えは増えました。これが余白設計の効き目です。
6|日々の出来事から学んだこと
ある利用者さんは、午前中は検査、午後はカットに切り替えると集中が続きました。
別の方は、「自分が呼ばれたかどうか」が不安の種。名前が似たスタッフがいるため、遠くからではなく視界に入り、本人と目が合う距離や場所から呼ぶ(これは当たり前)ことを再共有。返事してもOK(あー、ごめんなさい!●●さんでした! と冗談で周囲の笑いを誘うこともあり)という合意も作りました。
また、「良品か不良品か分からない」という声には、エラー見本・写真マニュアル・確認導線の三点セットで対応。
いずれも、努力を増やさずに成果を増やす工夫です。
7|よくある質問(FAQ)
Q. 努力を求めないと、甘えになりませんか?
A. 努力を免除するのではなく、出しやすい条件を整えています。条件が整うと、本人の意欲はむしろ見えやすくなります。
Q. 個別配慮は“特別扱い”になりませんか?
A. 同じものを配る公平ではなく、必要に応じて支える公正を重視しています。これは就労の場でも一般的になりつつある考え方です。
Q. 家族として何を手伝えばいい?
A. 睡眠・食事・通所の見通し。この3点のサポートが最大の支えになります。具体的には、通所前日の持ち物チェックと当日の出発時刻の共有など。
8|まとめと次の一歩
「努力」は尊い。でも、努力を出せるかはあなた次第ではない。土台次第
Lumoは、その土台づくりを“支援”と呼びます。
あなたの現場やご家庭でも、時間の分解/導線の選択肢/見通しの見える化──どれか一つから始めませんか。
関連リンク
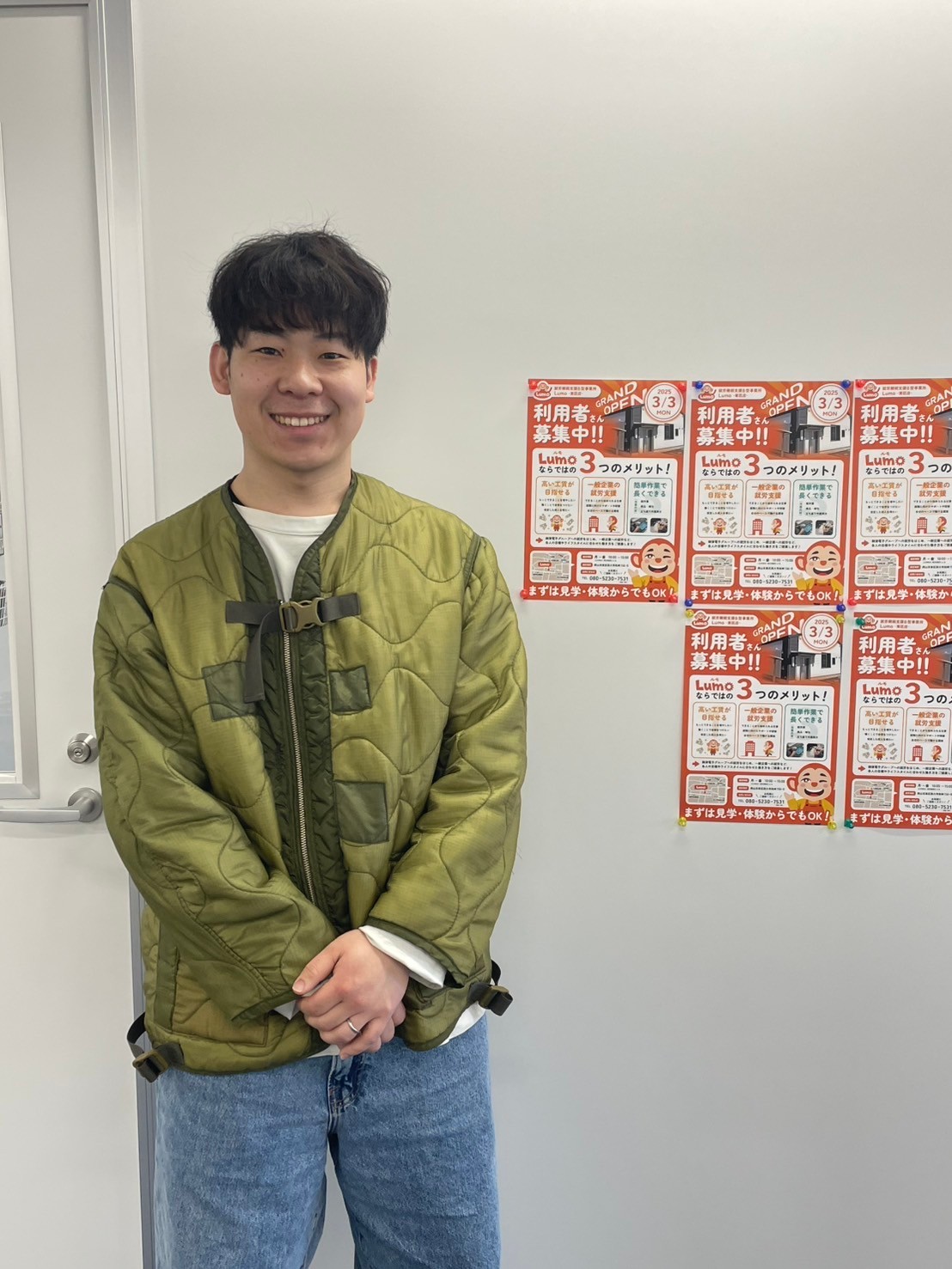
はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です
Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。
――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。
定員20名なのに見学待ちの行列。
毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。
どうして行列ができるの?
- “支え合う”という文化
ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。
だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。
▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)
- 仕事を“楽しく”設計
ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。
「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長
初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。
成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。
これからブログで発信すること
- 利用者さんの成長ストーリー:
小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:
就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:
見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。
最後に
「みんな違って、みんながいい」――
そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。
これは私の原動力であり、Lumoの未来です。
ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!
